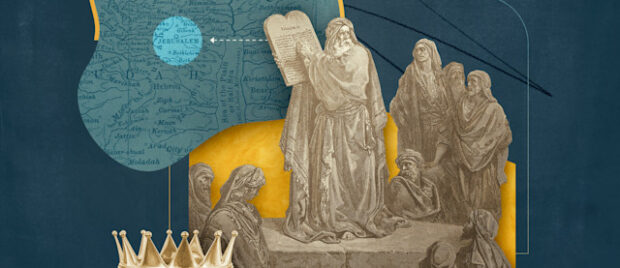使徒ペテロについて知っておくべき五つのこと
2024年07月10日(木)
出エジプト記について知っておくべき三つのこと
2024年07月14日(木)創世記について知っておくべき三つのこと

現代創世記を読む人の多くは、これが精密に構成された文学作品であるとは捉えていないでしょう。私たちは、この書物を断片的に読むことに慣れてしまったようです。クリスチャンが公の場で、または個人的に聖書を読むとき、その読み方は創世記を一つのまとまった書物として理解すべきだという考えからは離れています。その結果、創世記の重要な側面が見逃されているのです。ここでは、創世記の三つの重要な特徴を確認していきましょう。
1. 創世記は一つの特徴的な家系の歴史をたどるために構成された
第一に、創世記は一つの特徴的な家系の歴史をたどるために構成されました。家系図では各世代に一人の男性(「族長家系」)にスポットが当てられています。ギリシア語のgenesisは「系図」を意味します。この族長家系はアダムから始まり、三人目の息子セツを経て、ノアに至ります(創世5:1-32)。ノア以降、族長家系はセムからアブラハムに至ります(創世11:10-26)。その後、物語のペースは落ち、この特徴的な家系に対する関心は途絶えることはありません。サラが不妊であったことは、族長家系存続の大きな危機となりますが、神がサラに息子イサクを与えられました。イサクからは、族長家系はエサウの双子の弟ヤコブ(後にイスラエルと呼ばれる)へと繋がります。本来はエサウが族長家系において次に来るはずでした。しかし、エサウは自分の長子の権利を軽んじ、族長家系に入りたいと願っていた弟のヤコブに、煮物一杯と引き換えにその権利を売ってしまいます(創世25:29-34)。ヤコブから、族長家系はヨセフへと関連づけられ(一歴代5:1-2参照)、ヨセフの末の息子エフライムに至ります。ヤコブはエフライムを、兄のマナセより優先しました(創世48:13-20)。興味深いことに、創世記はしばしば、長子が族長家系から外れる理由の手がかりを示しています(例えば、ルベンとビルハの不適切な密通;創世35:22参照)。
ヨセフが兄たちよりも優先されるかたわら、創世記は族長家系の歴史における重要な展開を差し込みます。創世記38章はユダに焦点を当てています。この章はヨセフの人生の物語を中断させる部分として軽視されやすい箇所ですが、族長家系に着目して読むと、創世記38章はユダの血統をたどる物語であり、神がユダの長男と次男を殺した時点でその血統の危機が垣間見られます。タマルによる異常な介入によってユダの人生は大きく変化し、結果的に双子が生まれます。この双子の誕生においても、ペレツが割り込んでゼラフの前に生まれてきたため、またもや長子相続制(長子の相続の権利)の原則が逆転しました。その後、ヤコブはユダに祝福を与え、その子孫に王権があるようにと宣言します(創世49:8-12)。この祝福は、数世紀後のサムエルの時代に実現することになります(詩篇78:67-72参照)。
なぜ、この族長家系がそれほど重要なのでしょうか? 創世記3章15節に始まる族長家系は、エバの後の子孫が神の敵である蛇を打ち倒すことを示しています。創世記が展開するにつれて、この約束された子孫は、仲介者として神の祝福を地上の国々にもたらし、神の完全なる代理人として神の国を建てあげる王であることがわかってきます。このような期待を抱き、創世記はイエス・キリストの到来を待ち望んでいるのです。
2. 神はアブラハムと永遠の契約を結び、アブラハムを多くの国民の父とする
第二に、創世記の族長家系を土台として、神はアブラハムと永遠の契約を結び、アブラハムが多くの国民の父となることを約束されます(創世17:4-5)。創世記を読む人の多く、そして学者の多くは、創世記15章の契約に注目します。これはアブラハムがイスラエルという一つの国の父になるという約束です。しかし、創世記17章の契約は、先の契約より圧倒的に重要であり、先の契約を組み入れた上でアブラハムの父性を諸国民に拡大するものです。この父性は、生物学的なものではなく霊的なものです。割礼の契約は、アブラハムの子孫の一人が、そのお方を王と認める人々に神の祝福をもたらすことを保証しています。そのため、イサクからヤコブ(創世27:29)、そしてヤコブからユダ(創世49:10)へと与えられた族長の祝福には、諸国民が将来の王に仕えるという期待が反映されています。新約聖書に目を向けてみると、使徒ペテロはイエス・キリストこそがアブラハムに与えられた約束を成就される方であると述べています(使徒3:25-26)。同じように、使徒パウロによると、割礼の契約に伴う約束は、異邦人が神の民に含まれることの根拠となっています(ガラテヤ3:15-29)。
3. 祝福というテーマは、最終的にイエス・キリストに至る族長家系につながっている
よく見過ごされてしまう創世記の三つ目の特徴は、祝福というテーマが、最終的にイエス・キリストに至る族長家系につながっているということです。エデンの園で、アダムとエバの行動は人の人生に悪影響を及ぼす神の呪いをもたらします。それとは対照的に、神のアブラハムに対する召命は、地のすべての部族に神の祝福がもたらされる可能性を示しています(創世12:1-3)。この祝福というテーマは、後に、アブラハムの子孫と結びつけられます(創世22:18)。この祝福は、イスラエル民族全体を通してもたらされるものと考えられがちですが、創世記は祝福の源を族長家系に続く子孫に限定しています。この祝福(berakah)は、長子の権利を持つ人物(bekorah)に結びついているからです。このことは、ヤコブとエサウの物語に顕著に現れています。ヤコブは祝福をもたらす者であり、叔父であるラバンもその事実を認めています(創世30:27-30)。同様に、ヨセフもまた祝福をもたらす者ですが、それは創世記39章5節でポティファルの「家や野にある全財産」に関する記述に明確です。その後ヨセフは投獄されるものの、最終的にはファラオの父として高められ(創世45:8)、深刻な飢饉のあいだも数多くの国々に祝福をもたらします。
創世記を全体的に読むと、この書物がいかに巧みに構成されているかがわかります。文学的に多様な要素を含む創世記は、さまざまな題材を駆使し、私たちすべてに神の祝福をもたらすお方であるイエス・キリストを注意深く指し示すよう、統一されたメッセージを伝えているのです。
この記事はリゴニア・ミニストリーズブログに掲載されていたものです。